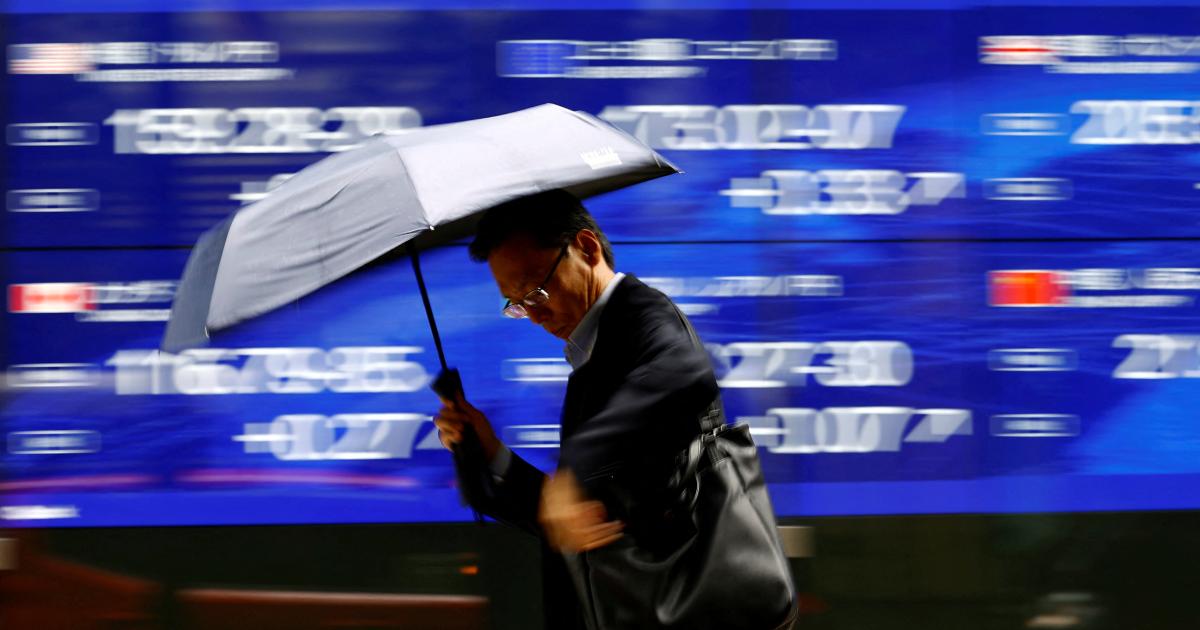アメリカの政策立案者の間には、中国がロボティクスや人工知能などの重要な技術でアメリカを追い越すのではないかという不安が広がっている。
これは、1980年代に日本が支配的だった時代にも見られた懸念である。
当時のベストセラー書籍『日本は一番』やPBSのドキュメンタリー「戦争に負けた日本」は、日本の経済的優位性を警告していた。
シリコンバレーは衰退しているように見え、アメリカの製造業者はDRAMなどのメモリーチップ市場から撤退していた。
デトロイトは、トヨタのリーン生産方式に苦しんでおり、アメリカ市場における自動車と消費者電子機器を支配しているように見えた。
しかし、1995年には情報技術ブームが生産性統計に現れ、アメリカは決定的に先行していた。
アメリカの対日競争における予測は、しても未遂なく、日本がつまずいたわけではなく、アメリカがコンピュータ時代の幕開けにおいて重要な分野で際立ったからである。
当時のアメリカは関税壁を築くことや国家的チャンピオンを支えることで日本に勝ったわけではなく、オープンな競争とテクノロジーが変化する中でサプライチェーンを再編する柔軟性によってリーダーシップを確保していたのである。
現在、トランプ政権はこの教訓を忘れてしまったように見える。
ドナルド・トランプ大統領は、インテルのCEOに辞任を求めており、特定のNvidiaやAdvanced Micro Devicesの中国向け半導体販売に対して15パーセントの送金を求め、また日本企業の新日本製鉄によるU.S. Steelの買収の一環として「ゴールデンシェア」を創設した。
このような恣意的な介入は、日本に対抗する上でのルールに基づくアプローチを破ってしまう。
アメリカが日本を超えた理由は歴史以上のものであり、中国に対する課題への指針ともなる。
日本の経済モデルは一時的には不可能に思えたが、今の中国も同様である。
しかし、アメリカ市場をより革新的にし、競争力を高めるためのツールは変わっていない。
アメリカは、自国の政策を捨てるべきではない。
日本の戦後の「奇跡」は、1950年から1973年の石油ショックまでの間、年間約8パーセントの実質GDP成長を達成した。
その根底には、明治時代(1868年〜1912年)のリーダーたちが西洋の知識を吸収する国家を築いたことがある。
特にイギリスからの知識を取り入れるために、国家翻訳局を設立し、数千人の外国の教員を招聘し、技術用語を標準化した。
高度に集権化された国家は、鉄道や電 telegraph networkの整備を進め、投資家に対する利益保障を行い、官僚と密接に協力する家族経営の複合体(財閥)を生み出した。
第二次世界大戦後、東京は19世紀のこのモデルを拡張し、厳格な国家と企業の提携を実現し、最先端技術を迅速に取り込んで適応し、スケールアップした。
1951年の日米平和条約は、アメリカからの技術と技術支援へのアクセスをもたらしたが、経済政策を監督する強力な官庁である通商産業省も企業が外国の知識をすばやく吸収し改善できるよう調整する重要な役割を果たした。
市場アクセスを特許ライセンスの義務づけに条件づけ、特にIBMやテキサス・インスツルメンツとの交渉では、最先端の革新が日本企業に流れるようにしていた。
IBMの例では、通商産業省の企業局長であった佐橋茂は、同社の日本でのビジネスを拒否することを脅しに使い、地元企業に技術をライセンスさせるようにした。
その結果、IBMは技術ライセンスを契約し、わずか5パーセントのロイヤリティで現地企業との契約を結ぶことになった。
一方、日本の製造業は、継続的改善(カイゼン)、リーン生産、ジャストインタイムの納品を重視した。
企業再編成は、ザイバツに代わり、互換可能な企業グループ(系列)が台頭する中で、それらの原則を進展させた。
1960年代半ばまでに、6つの系列が日本の企業の約30パーセントをコントロールし、複雑な製造協力で外部からの参入を困難にした。
1980年までに、このモデルは驚異的な結果をもたらした。
日本の自動車労働者は、その時にアメリカの同業者よりも17パーセント生産性が高く、フォードやゼネラルモーターズは13億ドル以上の損失を計上した。
日本の半導体産業では、チップメーカーが設備供給者と緊密に協力し、生産の欠陥を排除していた。
1989年には、日本は世界の輸出国になり、アメリカの輸入の4分の1を供給し、世界の需要の約半分を満たすことになった。
一方、アメリカの市場シェアはわずかに57パーセントから40パーセントに減少した。
だが、日本に優位性をもたらした制度が急激な変化を妨げていた。
国は他国の発明を吸収し洗練するのが得意で、成熟したハードウェアの時代にはプロセス効率への研究開発の大部分を集中していた。
これは、ソフトウェアやeコマースの移行に対して、日本が悪い評価を受ける根本的な原因である。
産業構造は、系列間の内部協力を容易にし、外部からの参入を難しくしていた。
カルテルのような調整が許容され、反トラスト法の執行は弱かった。
アメリカの競争制度と比べると、日本のシステムは既存企業を優遇する傾向があった。
1989年までに、日本の裁判所は反トラスト法が導入されてからわずか6件の刑事訴追を開始したが、同期間中にアメリカ政府は2,271件の反トラスト訴訟を提起した。
このようなアメリカの介入は雇用を増やし、事業の設立を促進した。
アメリカの反トラスト法は、スケールと緊密な調整を抑制したが、競争のある市場を保ち、新しい企業の参入を促した。
この理由から、アメリカは最終的に先を行くことができた。
日本の戦後の躍進の制度的基盤は19世紀にさかのぼるが、アメリカのダイナミズムの根源も同様である。
19世紀後半に企業の巨人と全国的なトラストの台頭が、競争と革新を締め付ける集中した権力に対する恐れを引き起こした。
この反応として、1890年に制定されたシャーマン反トラスト法が、独占と取引の制約を禁止した。
25年後の1914年には、クレイトン反トラスト法と連邦取引委員会法が制定され、反競争的合併に関する規則が強化され、FTCが不当競争を監視するために設立された。
これらの法律の技術開発への影響は永続的かつ具体的であった。
連邦政府の圧力を受けたデュポンなどの企業は、買収依存型の成長を放棄し、社内の研究開発を拡大した。
反トラスト法もコンピュータのボトルネックを解消した。
IBMは自らの市場優位性を利用してソフトウェアとハードウェアを束ね、外部の参入障害を高めていた。
しかし、1968年には反トラスト圧力の下で、ソフトウェア部門をスピンオフし、新しい市場が誕生し、スタートアップ企業の台頭を助けることとなった。
同様に、AT&Tの反トラスト事件は1984年に同社を分割し、インターネットが出現する直前の通信業界における単一の企業の障壁を取り除いた。
競争力のある分割された通信市場が、実験の急増を可能にした—電子メール、ファイル転送、コラボレーションツール—は、ユーザーや新企業によるものだった。
その後、企業は自らが行っていた機能を外注し、新しい供給者や商品スタートアップが参入できる余地を生み出した。
重要なことに、それらのスタートアップは従来の大企業に売るのではなく、公開市場を通じて規模を拡大することができた。
2000年代初頭までには、ベンチャーキャピタルに支えられた企業が市場資本総額の約3分の1を占めるようになった。
この波は、アメリカの生産性を回復させ、日本の発展を停滞させた。
アメリカの企業は、日本の国内市場を再現しようとするのではなく、生産をモジュール化し、オープンスタンダードを採用し、デザインに特化し、グローバルなバリューチェーンを利用してコストを削減し、柔軟性を高めた。
1990年代の中盤までに、中国の組立ハブはアメリカの革新の延長となり、台湾には数千の機敏な部品メーカーが存在した。
アメリカ企業の中国本土、香港、台湾との深い統合は、日本のコスト優位性を erode し、アメリカのソフトウェア、サービス、プラットフォームへの転換を加速させた。
中国の経済的台頭の鍵は、日本やアメリカとは異なる。
中国の指導者、鄧小平は1978年に日本を訪問し、日本のプレイブックを模倣しようとしたが、官僚間の争いが障害となり、計画経済の困難な政府の技術輸入スキームが誤作動した。
1979年には特別経済区が設立され、広東省や福建省で市場経済を試行し、ビジネスに優しい規制を設けた。
これらの南部地区では外国資本を誘致し、中国の電子機器とコンピュータ産業の中心地となった。
中国の主要コンピュータ企業であるレジェンド(現在のレノボ)やグレートウォールは北京に設立されたが、やがて重要な生産と研究を南に移転し、グローバルなサプライチェーンに組み込まれた。
2000年代初頭には、戦略的産業政策はほとんど後退していた。
中国の成長を促進したのは、数え切れないほどの地域実験であり、中央政府がその成功事例をスケールアップすることができたことだった。
1978年から1979年にかけての農村改革により、農民は割当を超えて余剰生産物を販売できるようになり、鄧の二重軌道アプローチが形成された。
これにより完全な市場経済には変わらなかったが、計画の配分と市場の販売の両方が可能になり、市場経済の効果を模倣する移行機関を創り出した。
数万の地方政府が投資や人材を競い合っており、リーダーのキャリアが成果を出すことに依存しているため、企業のように振舞った。
しかし、中国共産党は最も重要な手段、すなわち人事権を保持している。
地元のリーダーを任命、報奨、懲戒することにより、中央政権は市場経済に似たインセンティブを導入しつつ、上に政治権力を維持した。
この結果、企業の動的性が減少し、生産性が低下している。
政治資本主義は追いつき成長には適しているが、技術の最前線に近づくにつれて、革新は不確実性に依存し、そのため管理が難しくなり、官僚主義に弱くなる。
革新の成果が不確実で計量できない理由から、パフォーマンス目標は不正を招く恐れがある。
公式は特許数などの数値目標を達成できても、真に新しい技術を育てることには結びつかない。
通常であればより分散化が求められるこの課題、すなわち競争を促進し、地域の試行錯誤の余地を広げる政策は、より中央集権化することで対処された。
2008年に全国人民代表大会は反トラスト法を通過させたが、当局はこれを外国企業や強力な企業家の制裁に対して選択的に適用し、国有企業を保護している。
民間部門に対する支配は他の方法でも厳しくなった。
北京はアリババ、バイトダンス、テンセントなどの企業の株を取得し、政治的に結びついた市民はそのポートフォリオが大幅に成長している。
さらに、国は国家の目標に沿った方向での革新を試みており、2010年には国家チャンピオンを作るための運動や、2006年には科学技術の研究開発を拡大する運動を行っている。
最近では「中国製造2025」や「インターネットプラス」などのプロジェクトが進められ、これにより半導体、人工知能、バイオテクノロジー、先進ロボティクスへの資金が数兆元に上る助成金や税控除、国家から導かれるベンチャーキャピタルが導入されている。
北京は共通の繁栄や技術的自給自足に関するミッションの周りに経済を構築して監視を強化し、より国有企業が国家目標に合わせやすく、一方で政治的干渉を恐れた leading private firmsは国家のつながりのある投資者を避けるようになった。
権力が北京に集中するにつれて、地域の実験は減少し、パフォーマンスから政治的忠誠心へと責任が移行した。
国有企業は依然として弱い革新者であり、デジタルプラットフォーム、eコマース、AIのようなダイナミックな分野からも存在感が欠如している。
民間の国家チャンピオンたちが広範なダイナミズムを代替することはできず、また小さな民間企業や外国企業は新規性の通常の源泉となるが、上昇する障壁に直面している。
2000年代初頭以降、ビジネスのダイナミズムは衰え、生産性は低下している。
2007から2009年の世界金融危機の後にはマイナス成長となり、2010年代を通して著しいスローダウンが続いている。
このスローダウンの一部は、中国が経済成長を遂げる過程で自然なものであるが、その動向は日本、韓国、台湾のようなより高い所得レベルの下ででの停滞を示している。
ワシントンは、中国の台頭とアメリカがかつて日本を超えた方法から適切な教訓を引き出さなければならない。
1980年代の日本と同様に、中国は製造業の強国であり、価値の高い製品へと進化を遂げている。
その利点は急激な革新にあるのではなく、規模、統合、迅速な反復にある。
例えば、高速鉄道を考えてほしい。
中国はフランスのアルストム、日本の川崎、ドイツのシーメンスからの外国技術を組み立て、それを圧倒的なスピードで拡張し、2008年には最初の旅客専用ラインを開通させ、昨年末までに約30,000マイルの世界最大のネットワークを構築した。
中国は、通信、太陽光発電装置、バッテリー製造においても同じ脚本をたどっている。
アップルが中国のスマートフォンエコシステムにしたこと—中国のサプライヤーを訓練し、後にファーウェイなどの企業と提携させた—を、テスラは今、中国の電気自動車生産者に対して行っている。
中国は後発企業として、現代のシステムに一気に飛びつくことが多い。
例えば、北京大興国際空港は顔認識入場システム、地熱ヒートポンプ、無線周波数を使用した荷物追跡などを備えている。
一方、アメリカはレガシーインフラのアップグレードに苦労している。
アメリカのシステムは、選挙によって選択される大統領、二院制の議会、独立した司法制度、地方自治体の政府など、権力を分散させているため、多くの人々が行動を妨げることができる。
これらの拒否権は保護として設計されているが、しばしば決定を遅らせ、革新技術や改革の採用を妨害している。
アメリカにとって、政治的に魅力的な反応は、国を保護し、既存企業を保護することだが、それは未来を譲ることである。
より良い道は、分散した相互依存を促進することである。
特定のノード、例えば重要な鉱物に対する中国への暴露を減らす正当な安全上の理由はあるが、自給自足は幻想に過ぎない。
北京の権力を和らげる方法は、貿易関係を絶つことではなく、メキシコや韓国などの同盟国との統合を促進することである。
歴史的に見て、アメリカは自らをグローバルネットワークに結びつけ、それを自らの利益に転化することで繁栄してきた。
市場を競争可能に保つことは同様に重要である。
コンピュータ革命は、アップル、グーグル、マイクロソフトのようなスタートアップが公開して独立した企業として存続したからこそ可能であった。
1980年代と1990年代には、より容易な公開株式の発行とベンチャーキャピタルの深化が、初期の株式公開のデフォルトとなっていた。
しかし、2000年代初頭以降、より厳格な投資家保護(特に2002年のサーベンス・オクスリー法)が実施され、公開企業の監視が強化され、CEOやCFOは金融報告を個人的に認証しなければならず、年に1回不正防止策が実際に機能している証拠を必要としたため、新規企業が公開する際のコストとリスクが上昇した。
同時に、より許可された合併審査プロセスと反トラスト法の施行により、顕著なプラットフォームが急成長する企業を買収しやすくなった。
その結果、競争は冷え込み、アメリカのビジネス環境は過去のものとなっていた。
変わったのは教義だけではなく、インセンティブもである。
バッキリー対ヴァレオ(1976年)の最高裁判決以降、政治的支出の制限が言論の制限と同視され、企業からの資金提供が急増した。
1980年から2012年の間に、上級経営者からの寄付は320倍に増加し、その半分は上位0.01パーセントの寄付者からのものである。
ロビー活動支出は1990年代後半以降2倍以上に増加し、これは主に大企業によるものである。
通常の産業における上位4社が約15パーセントの収益を占める一方で、これらの企業は約35パーセントの選挙寄付と約45パーセントのロビー活動支出を供給している。
この圧力は機能しており、連邦取引委員会や司法省は既存の反トラスト法の施行をほとんど行わなくなっている。
より競争力のあるシステムを再構築するには、新しい企業の公開のコストを下げ、成長企業の独立したスケール成長を促すように、合併の精査を強化する必要がある。
直近の試金石はAIである。
OpenAIはマイクロソフトとの深いパートナーシップを通じて、現在市場の約2/3を占めている。
支配的なプラットフォームも、AIエコシステムへの主要な投資者およびパートナーである。
アマゾン、グーグル、メタ、そしてマイクロソフトは、主要なAIスタートアップと何年も支援契約を結んでいる。
そして、最も重要な質問は、主要研究所が公開して独立を維持できるかどうか、または独占的なパートナーシップや買収主導の統合に至るかである。
統合は、単にリソースを集めることだけがAIの進展を促すのであれば、弁護しやすくなるだろうが、実際はアイデアと競争こそが最前線を押し広げている。
中国においては、AI、電気自動車、太陽光発電システムのように競争が激しい部門において、パフォーマンスが最も高いが、それらのセクターでの過剰供給は価格崩壊を引き起こし、北京が「無秩序な」低価格競争を取り締まることさえ促している。
対照的に、老舗の独占企業や国有企業が支配する分野はパフォーマンスが劣っている。
中国は日本ではない。その市場はより大きく、国家のサポートもより強い。
そして、アメリカにとって、この競争の安全問題のリスクも遥かに高い。
しかし同じルールが適用される:アメリカは要塞経済を拒否すべきである。
北京を真剣な競争相手と見なし、日本の成功モデルの模倣ではなく、違う方法で課題に対処する必要がある。
画像の出所:foreignaffairs