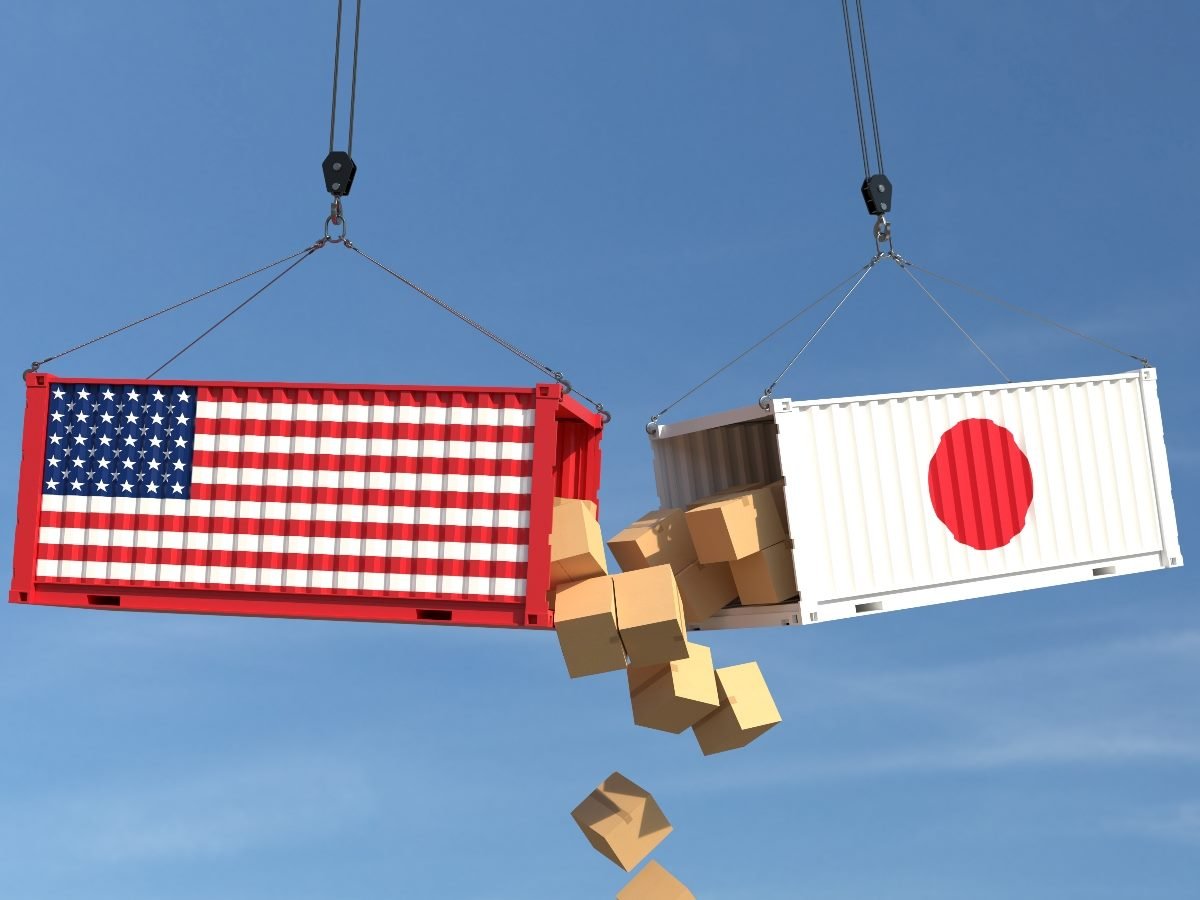2025年6月、私は東京で開催された第8回全国顧客体験フォーラムに出席し、Salesforce Japan、NTT Marketing Act ProCX、TechMatrix、Genesys、TransCosmos、およびToyo Keizaiが後援するイベントに参加しました。
800人以上が対面またはオンラインで参加し、アメリカ企業にとっても示唆に富むいくつかのトレンドが報告されました。
フォーラムでの重要な問題
日本の企業がAIを積極的に取り入れ、多くの企業が顧客体験の向上を目指している一方で、アメリカの企業はより慎重な姿勢を見せています。
日本企業がAIを急速に導入する中、アメリカ企業はその導入において慎重です。
日本では、AIを積極的に活用し、技術を通じて顧客が直面する可能性のある問題を予測し、常に「顧客の一歩前を行く」努力をしています。
顧客フィードバックの迅速なループも確立されており、迅速な実験と継続的改善を通じて、顧客の問題を未然に防ぐための教育が進められています。
Fujitsuは、Salesforce AIが技術製造業者の重要な返品プロセスを円滑にし、顧客の状況に応じて返送料金を免除するなどの支援を行う事例を紹介しました。
AIエージェントは、顧客が不満を表明した際には、人間にエスカレーションすることも可能です。
このような物語は、新しい従業員の選定やフロントライン従業員、スーパーバイザーに権限を持たせるために活用され、競争からの障壁を形成しています。
また、企業内で容易にエスカレーションできるポリシーを推進し、消費者からのハラスメントから社員を保護する法律に対処する必要があると言及されました。
日本とアメリカにおける消費者の問題の違い
アメリカと日本における消費者の問題には顕著な違いがあることが分かります。
日本での顧客の怒りの事例は、無理な要求に伴うもので、顧客が従業員に対してひざまずくよう要求する事例も存在します。
一方、アメリカでは不満が高まり、UnitedHealthcareのCEOに対する暴力的な事件などが報じられています。
アメリカのビジネスに対して、悪質なサービスを故意に提供して利益を最大化しているという厳しい批判が上がっています。
日本とアメリカの顧客の怒りに関する研究は、二国間で根本的な違いを示していますが、顧客の苦情行動においては多くの共通点も持っています。
日本での研究では、5000人の消費者を対象に調査が行われました。
その結果、日本では深刻な問題に直面する消費者が約40%に対し、アメリカでは75%に達しました。
日本の上位の問題には、eコマースでの誤解を招くマーケティングや製品の取り消しが含まれていますが、アメリカでは自動車、インターネットや携帯電話、金融サービスに関連した不具合が上位を占めます。
苦情の発生率は、アメリカが80%に対し、日本では50%とされます。
重要な点は、日本人消費者の多くが手間やフリクションを理由に苦情を申し立てないのに対し、アメリカの消費者は、申し立てをしても何も変わらないと感じていることです。
アメリカと日本の苦情行動の比較
以下の表は、アメリカと日本の消費者の苦情および動機の主要な違いを示しています。
側面 | アメリカ | 日本
——————–|—————-|—————-
深刻な問題の報告率 | 約75%の消費者| 約40%の消費者
上位の問題 | 自動車、インターネット/携帯電話、金融サービス | 誤解を招くeコマースのマーケティング、製品の取り消し
苦情率(深刻な問題)| 80% | 50%
苦情を申し立てない理由 | 効果がないと感じる、エスカレーションの方法がわからない | サービスプロセスの手間
主なチャネル | チャット、デジタルファースト | 依然として電話が主流
結果に対する不満 | 60%が不満| 67%が不満
顧客の怒りの要因
両国で共通するのは、顧客が人間に容易に接触できないことと長い待機メッセージがあることが主に怒りの原因であるという点です。
CCMCの怒りに関する調査によると、顧客の怒りや不満は、接触の困難さや長い待機時間から引き起こされています。
調査によると、アメリカの約3分の2が組織に対して怒りを経験したと報告し、43%がサービス担当者に対して大声で怒鳴ることがあると語っています。
また、9%は特定の企業に対する復讐を考えていると答えています。
苦情を申し立てない動機は両国で大きく異なります。
アメリカの非苦情者は、問題の解決に向けて行動を起こしても何も変わらないと考えており、結果としてお金よりも時間を価値として重視する傾向が見受けられます。
一方、日本の非苦情者は、苦情申し立ての手間を理由に黙っていることが多いです。
苦情チャネルの進化
両国で苦情申し立ての手段が進化しています。
アメリカでは、デジタルチャネルが主流であり、チャットがメールやウェブサイトのメッセージを上回る人気を博しています。
アメリカの消費者は、チャットが比較的迅速に応答され、やりとりの記録を残すことができるため、価値を見出しています。
日本では、依然として電話が主要な手段ですが、デジタルチャンネルの利用は増加しています。
両国のほとんどの苦情申し立て者は、不満を抱え続けており、アメリカでは60%、日本では67%と報告されています。
満足度の低い顧客は、70-90%の離脱率を示し、また負の口コミが広がってしまいます。
日本では、満足した顧客は忠誠を保ち、2人に良い口コミを伝える傾向があります。
AI戦略:日本とアメリカの対比
アメリカ企業は、急騰するサプライチェーンコストという課題に直面していますが、日本企業はコンタクトセンターの人手不足という課題に取り組んでいます。
Salesforce Japanは、AIを用いたクロスチャネルサービスを示すプレゼンテーションを行い、CRMおよび過去の取引履歴を参照して顧客関係を理解し、プロアクティブなサポートを提供する方法を示しています。
アプリケーションは、顧客サービスだけにとどまらず、マーケティングや営業活動を含む分野にも広がっています。
顧客の質問に対して事前に教育を提供することで迅速な onboardingが実現されます。
過去のサポート、インストア履歴、電話、チャット、ウェブサイト使用履歴を一元管理することで、自己指導型のAIエージェントによる完全自動化が目指されています。
保険会社や技術企業のケーススタディでその効果が示されています。
AIに対する消費者の認識
カンファレンスでは、日本の消費者の半数未満がカスタマーサービスにおけるAIの活用に気付いていないという調査結果が示されました。
AIを意識している消費者の中でも、その使用をサービス向上のためのポジティブなツールとして見なす傾向があります。
一方で、アメリカでは最近のミスにより、AIに対する消費者および企業の信頼が損なわれている状況があります。
日本企業は、顧客が好む自己解決の能力を高め、より正確かつ効果的にすることに注力しています。
顧客体験の設計と予防戦略
NTT Marketing Act ProCXは、AIの利用が効果的でないケースにおける詳細なCXジャーニーフローデザインを提唱しました。
AIの適用が難しい場合でも、CXデザインを通じてマネジメントに影響を及ぼすべきだと強調しました。
NTTは、AIが適用できる問題と適用できない問題の両方に対する問題と質問の予防を重視し、苦情処理よりも事前分析と行動が10-20倍のROIをもたらすと基づいた手法を強調しました。
日本はAIで遅れをとっているが、可能性を秘めている
日本企業はAI導入においてアメリカより約2年遅れているものの、現在急速に追いついています。
短期的には、特に慎重でなく急速に実行に移している意見もあります。
同時に、彼らはAIの成果と影響を厳密に測定し、継続的なフィードバックに基づいて迅速な調整を行っています。
この「失敗から学ぶ」アプローチによって、アメリカでのネガティブな影響を避けつつ、AIを日本の人々に導入できる可能性があります。
画像の出所:cmswire